電気施設管理の学習帳
目次
- 電力需給
- 日負荷曲線・負荷持続曲線
- 供給力と供給予備力
- 負荷率・需要率・不等率・設備利用率
- 電力系統の周波数調整
- 系統連系による広域運営
- 分散型電源との連携
- 電線路の絶縁性能試験の方法
- 電気工作物の保全
- 油入変圧器の絶縁劣化診断
- 高調波・フリッカ対策
電力需給
電力の需要は1日の間で大きく変動し、一般に日中に需要が最大となる。一方で、太陽光発電の大量導入に伴って、日中の発電量が需要を上回る事例も報告されている。需要電力の平準化や、電力の需給バランスの確保のために、揚水式発電が用いられている。また近年では、蓄電池などの電力貯蔵装置の技術が向上している。
天候の急変時や発電所の故障発生時にも周波数を標準周波数へと回復させるために、運転予備力(供給予備力のうち数分で運転が可能なもの)が確保されている。部分負荷運転中の水力発電機や火力発電機などが運転予備力の対象となる
電気は発生と消費とが同時的であるため、不断の供給を使命とする電気事業においては、常に変動する需要に対処しうる供給力を準備しなければならない。
しかし、発電設備は事故発生の可能性があり、また、水力発電所の供給力は河川流量の豊渇水による影響で変化する。一方、太陽光発電、風力発電などの供給力は天候により変化する。さらに、原子力発電所や火力発電所も定期検査などの補修作業のため一定期間の停止を必要とする。このように供給力は変動する要因が多い。他方、需要も予想と異なるおそれもある。
したがって、不断の供給を維持するためには、想定される最大電力に見合う供給力を保有することに加え、常に適量の供給予備力を保持しなければならない。
電力需給は、一般に最大電力バランスと電力量バランスとで表現される。最大電力バランスとは、需要の最大と供給能力を比較するもので、供給能力が需要を上回る分を供給予備力といい、これは供給信頼度に関わるものである。
また、電力量バランスは、月別・年度別に電力供給量の電源別の分担を決めるもので、発電所の運用計画などに役立てられる。
保有すべき供給予備力は、需給変動、地域間連系線の容量などを考慮して算出される。このうち、需給変動は、景気変動によって生じる需要変動(持続的需要変動)と、日々の需要変動及び電源の計画外停止や出水変動による供給力の低下を含む需給変動(偶発的需給変動)に分類される。地域間連系線の容量が増強されると、供給量不足時に電力融通が可能となり、増強前に比べて必要な供給予備力は小さくなる。
- 電験3種過去問【2022年(後期)電力 問11】(電力の需要と供給)
- 電験3種過去問【2019年法規 問10】(電力需給と広域的運営推進機関)
電験2種過去問【2022年法規 問7】(電力需給と供給予備力)
日負荷曲線・負荷持続曲線
横軸に時間を、縦軸に需要電力をとって表示した曲線を、日負荷曲線という。
この他に、日・週・旬・月・年を対象とする期間の電力需要について、その発生した時間とは無関係に大きい順に並び替えた曲線のことを負荷持続曲線という。負荷の特性を分析・調査するために使用される。
供給力と供給予備力
時々刻々変動する電力需要に対する供給力の運用上の分類と供給予備力について述べる。
- 次の三つに区分された供給力について、それぞれ➀日負荷曲線上の分担とその役割、及び➁対応する電源種別について述べる。
a. ベース供給力
➀日負荷曲線上の分担とその役割
1日の変動する需要のうち、ほぼ一定のベース部分を分担し、長時間安定的に発電する。
➁対応する電源種別
流れ込み式水力発電所、地熱発電所、原子力発電所及び高効率の火力発電所が充てられる。
b. ミドル供給力
➀日負荷曲線上の分担とその役割
ベース需要とピーク需要の中間部分を分担し、需要の日間変化に応じて、日間起動停止を行うとともに出力調整運転を行う。
➁対応する電源種別
ベース火力より熱効率が多少劣っても、毎日の起動停止の容易な火力発電所が充てられる。
c. ピーク供給力
➀日負荷曲線上の分担とその役割
1日の変動する需要のうち、需要が最も大きくなるピーク部分を分担し、急激な出力変化や負荷変動に対応する。
➁対応する電源種別
急激な出力変化能力を有する水力発電所のうち、調整池式及び貯水池式の一般水力発電所と揚水式水力発電所が充てられる。また、水力発電所以外では、ベース火力やミドル火力よりも熱効率が劣っても始動時間が短く負荷追従性のよい火力発電所が充てられる。 - 次の三つの供給予備力について、➀それぞれを必要とする対象要因、➁予備力を発揮するまでの時間特性、及び➂対応する発電所について述べる。
d. 待機予備力
➀必要とする対象要因
需要想定値に対する持続的増加、水力の渇水、停止までに相当の時間的余裕のある電源に対応する。
➁予備力を発揮するまでの時間特性
始動から最大出力まで数時間かかる。
➂対応する発電所
必要な出力到達後は長時間運転継続できる停止待機中の火力発電所が対応する。
e. 運転予備力
➀必要とする対象要因
天候急変などによる需要の急増や電源を即時又は短時間内に停止・出力抑制しなければならない場合に対応する。
➁予備力を発揮するまでの時間特性
10分程度以内の短時間で供給力増加が可能である。
➂対応する発電所
待機予備力が発電するまでの間、継続して運転できる部分負荷運転中の発電所が対応する。
f. 瞬動予備力
➀必要とする対象要因
電源脱落時の大きな周波数低下に対して、即座に出力増加しなければならない場合に対応する。
➁予備力を発揮するまでの時間特性
運転予備力の一部であるが10秒程度以内で対応する。
➂対応する発電所
運転予備力が発電するまでの間継続して運転できるガバナフリー運転の発電所が対応する。
負荷率、需要率、不等率、設備利用率
\(\displaystyle 需要率=\frac{最大電力}{設備容量}\)
\(\displaystyle 負荷率=\frac{平均電力}{最大電力}\)
\(\displaystyle 不等率=\frac{各最大電力の和}{合成最大需要電力}\)
\(\displaystyle 設備利用率=\frac{平均電力}{設備容量}\)
すなわち、
\(\displaystyle 設備利用率=需要率\times負荷率\)
デマンドレスポンス
電力システムにおいて、需要と供給の間に不均衡が生じると、周波数が変動する。これを防止するため、需要と供給の均衡を常に確保する必要がある。
従来は、電力需要にあわせて電力供給を調整してきた。
しかし、近年、電力供給状況に応じ、スマートに消費パターンを変化させること、いわゆるディマンドリスポンス(「デマンドレスポンス」ともいう。以下同じ。)の重要性が強く認識されるようになっている。この取組の一つとして、電気事業者(小売電気事業者及び系統運用者をいう。以下同じ。)やアグリゲーター(複数の需要家を束ねて、ディマンドリスポンスによる需要削減量を電気事業者と取引する事業者)と需要家の間の契約に基づき、電力の需要削減の量や容量を取引する取組(要請による需要の削減量に応じて、需要家がアグリゲーターを介し電気事業者から報酬を得る。)、いわゆるネガワット取引の活用が進められている。
電力系統の周波数調整
- 周波数の変動は、次のような問題が発生する恐れがあるため、周波数を一定の範囲内に調整する必要があり、電気事業法においても周波数の維持について一般送配電事業者の努力義務が規定されている。【電気事業法 第二十六条(電圧及び周波数)】
- 電気使用者側の問題の例
- 工場の精密機械の誤動作
- 高速度電動機を使用する紡績・製紙工場等での製品品質の低下
- 周波数低下による電動機の効率の低下
- 電気時計の誤差の増大
- 電力系統管理者側の問題の例
- 火力発電設備のタービンの振動
- 発電機補機の出力減退
- 電力会社間連系線の潮流の制御の困難化
- 電気使用者側の問題の例
- 電力系統の周波数は需給バランスの影響を受け、負荷が発電を上回る場合には周波数は低下する。
周波数変動に応じて出力調整を行う発電所を周波数制御用発電所という。我が国では、揚水発電所、貯水池式又は調整池式水力発電所と火力発電所の一部が周波数制御用発電所として利用されている。
電力系統の周波数制御
- 電力系統の周波数が規定範囲を超えて低下すると、電気使用側では精密機械の誤動作や製品の品質低下などの問題が発生する可能性がある。一方、このとき、電力供給側の汽力発電設備には以下のような問題が発生する可能性がある。
- 翼長の長い低圧タービン動翼に共振により振動が発生、又は補機の出力が低下して運転が停止する可能性がある。
- 系統事故を除く周波数変動の主な原因には、負荷の変動と再生可能エネルギー電源の出力変動がある。このうち、負荷の変動は、変動周期により次の a ) ~ c ) に大別される。 a ) ~ c ) について、以下のように発電量を調整する。
a ) 日間周期変化を持つもので工場の稼働、事務所の冷暖房、夕方の点灯などによって生じる負荷変動
➡予想日負荷曲線を作成し、発電事業者等の発電計画により対処する。予想から外れた部分については、調整力である水力発電所又は火力発電所等に指令して発電量を調整する。
b ) 数分~数十分ぐらいの比較的短時間の間に頻繁に起きる負荷変動
➡系統周波数を計測して基準周波数からの偏差を検出し、調整力である水力発電所又は火力発電所等に、変動分に応じた出力調整を自動で指令して発電量を調整する。
c ) きわめて短時間の偶発的な負荷変動
➡発電所の内、周波数が下がった場合に出力を上昇させ、周波数が上がった場合に出力を低下させるガバナフリー運転機能を有する発電機により発電量を調整する。 - 日本の電力系統では、連系状態に応じて、2種類の負荷周波数制御方式が採用されている。
a ) 制御方式の一つは定周波数制御である。この制御方式は交流単独系統、又は連携している他の交流系統に比べて、系統容量が大きい系統に採用されている。
b ) 日本で採用されているもう一つの負荷周波数制御方式は周波数バイアス連系線電力制御方式(TBC)
電力系統の負荷変動による周波数変化
電力系統の負荷周波数制御方式
- 定周波数制御(FFC)
- 系統周波数を検出する方式である。
- 系統周波数の規定値からの偏差を零にするよう自系統の発電電力を制御する方式である。
- 単独系統、又は連系系統内の主要系統で採用されている。
- 定連系電力制御(FTC)
- 連系線電力を検出する方式である。
- 連系線電力の規定値からの偏差を零にするよう自系統の発電電力を制御する方式である。
- 連系系統内の小系統側が主要系統との連系線電力を制御する場合に適している。
- 周波数バイアス連系線電力制御(TBC)
- 周波数と連系線電力を検出する方式である。
- 系統周波数の規定値からの偏差にバイアス値を乗じた値と、連系線電力の規定値からの偏差の和(差)を零にするよう自系統の発電電力を制御する方式である。
- 連系系統内の各系統が、それぞれ自系統で生じた負荷変動(需給不均衡)を、自系統で処理することを基本としている。
直流連系による広域運営
我が国の一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。)間の電力系統は、互いに接続されることで広域運営が行われているが、この系統連系の中には、直流周波数変換装置や直流送電線等、直流設備を介した直流連系が存在する。
周波数変換所
我が国の系統周波数は 50 Hz と 60 Hz に分かれていることから、広域運営のための周波数変換所が現在3箇所存在する。
- 佐久間周波数変換所
- 新信濃変電所
- 東清水変電所
直流連系の長所及び短所について以下がある。
- 長所
- 充電電流がないため、ケーブルによる長距離の連系が可能である。(ケーブルで送電する場合、充電電流に起因した無効電力発生がないので、そのための無効電力補償装置が不要である)
- 送電端と受電端との間の電圧位相差(位相角)に起因する安定度問題がないので、長距離大容量送電による連系が可能である。
- 交流系統の短絡容量が連系によって増大しない。
- 潮流を自由に、かつ高速に制御できる。
- 交流系統の事故が他の交流系統に波及しない。
- 送電線の建設費用が同等の交流と比較して小さい。
- 周波数の異なる系統を連系することができる。
- 短所
- 直流連系の両端に変換設備が必要で、その建設費用が大きい。
- 交流系統の短絡容量が小さい場合、電圧不安定問題、発電機軸ねじり(ねじれ)問題、及び高調波不安定現象を発生する可能性がある。
- 多端子系統の構成(多端子連系)の場合は、制御と保護が複雑になる。
- 交流のじょう乱で運転に影響を受ける。
- 他励式の場合、送電電力に応じた無効電力補償装置が必要となる。
- 高調波対策が必要である。
系統周波数が同じ電力系統間の連系であるにもかかわらず、直流を介した連系が三つ存在する。連系箇所及び、直流連系を採用するに至った最も大きな技術的理由は以下。
北海道ー本州間直流連系
採用するに至った最大の技術的理由は、海底ケーブルによる海峡横断送電であるため、交流連系での無効電力発生を回避できること。
紀伊水道直流連系
採用するに至った最大の技術的理由は、海底ケーブルによる海峡横断送電であるため、交流連系での無効電力発生を回避できること。
南福光直流連系
採用するに至った最大の技術的理由は、ループ系統での潮流制御の自由度確保。
周波数が同じ電力系統間の直流連系において、南福光直流連系所はBTB 方式と呼ばれる直流連系である。
BTB 方式による直流連系の設備構成上の特徴は、2組の交直変換装置を1箇所に設置し交直変換装置同士が背中合わせとなるような設備構成(Back to Back)となっており、交直変換装置間に直流送電線がないことである。
BTB 方式による直流連系は、我が国では現在、隣接する一般送配電事業者3者間の電力系統の連系において1箇所の連系所(南福光連系所)に採用されている。この場合において、交流連系ではなく直流連系が採用された最も大きな技術的理由は、交流連系とした場合、一般送配電事業者3者間にまたがる交流ループ系統になり、常時の潮流制御が困難になるためである。
連系系統の電力不足確率
分散型電源との連系
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン(資源エネルギー庁)
事故波及防止リレーシステム
電力系統に発生した事故(部分的事故が)を事故除去リレーの働きによって高速で除去することで、通常は事故点を含む最小限の範囲の設備が停止することとなるが、系統及び事故の様相(不安定現象を含む)によっては、系統全体に事故の影響が波及拡大し、広範囲な停電を起こす場合があることから、事故波及防止リレーシステムが導入されている。事故によって次の 1. ~3. の事象が発生した場合には、下に述べる事故波及が発生する可能性があり、その事故波及を防止するために、事故波及防止リレーシステムによって下記の制御を行う。
- 送電線等の過負荷
事故により送電線や変圧器が停止し、他の健全設備の過負荷が発生した場合、過負荷になった設備の破損等による事故の発生、又は、破損等を回避するための設備停止によって、大規模な停電に至る可能性がある。また、ループ状やメッシュ状の系統では、過負荷になった設備の停止により、他の設備が過負荷となり、次々と設備停止を余儀なくされる可能性もある。
このような事故波及を防止するため、発電機出力又は負荷の抑制や遮断によって、送電線や変圧器を通過する電流を抑制する。 - 周波数低下
系統事故(及びその波及)により大量の電源が脱落し、大幅な需給アンバランスが生じた場合には、通常の制御では対処できない急激かつ大幅な周波数低下が発生し、これが発電プラントの安定運転限界を超過すると、連鎖的な発電機の脱落に繋がる可能性がある。
このような事故波及を防止するため、一部の負荷を遮断することで周波数の維持を図る。さらに、この対策によっても周波数の回復が困難で周波数低下状態が継続する場合には、連系系統を分離したり、適当な近傍負荷を有する局地火力系統を分離して単独系統として安定運転を維持させたりするなどにより、事故の影響による停電等が電力系統全体に及ぶことを回避する対策も採用されている。 - 発電機の脱調
事故除去の遅延や失敗によって発電機が脱調に至った場合、脱調の電気的中心付近の電圧が大きく低下することから、これを放置すると、他の発電機の電気出力の低下により次なる脱調が起こるという連鎖的な脱調現象が発生する可能性がある。
このような事故波及を防止するため、発電機の脱調が予測される場合に一部の電源の遮断を行って脱調現象の発生を防止する、又は、発電機の脱調が発生した後にこれを速やかに検出して脱調の電気的中心の両端で系統を分離することでそれ以上の進展を防止するといった制御を行う。
事故波及防止リレーシステムについて。
- 事故波及防止リレーシステムが適用対象とする系統の異常現象(不安定現象を含む)のうち3種類を挙げよ。
- 系統周波数の異常
- 安定度の喪失
- 過負荷の連鎖
- 電圧不安定現象
- 上記の異常現象に対し事故波及防止リレーシステムはそれぞれどのような動作をするか。
- では、周波数の異常低下に対しては、揚水発電所が揚水している場合は揚水遮断し、次には負荷遮断を適切に行う。
- では、該当する電源系統の発電制限、発電遮断などにより電力動揺を抑制する。
- では、該当する系統の発電制限、発電遮断、負荷遮断などを適切に選択あるいは組み合わせて実施し、過負荷を抑制する。
- では、該当する負荷系統において調相設備の投入、負荷遮断を適切に行い電圧低下を抑制する。
- 事故波及防止リレーシステムにおいて制御量を決定する方式には、動作原理から見ていくつかの方式が存在する。
事故波及防止リレーシステムにおいて制御量を決定する方式には、以下の3種類がある。- 系統じょう乱に発展し得る事故を想定して、事前情報からあらかじめ制御量を決定しておく事前演算方式。
- 事故中及び事故後の情報をもとに演算を行い、制御量を決定する事後演算方式。
- 特に演算を伴わない設備事故除去リレーと同様な構成のリレー形の方式。
保護協調
- 受電設備を含む配電系統において、過負荷又は短絡あるいは地絡が生じたとき、供給支障の拡大を防ぐため、事故点直近上位の遮断器のみが動作し、他の遮断器は動作しないとき、これらの遮断器の間では保護協調がとられているという。
- 地絡の発生個所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するため地絡方向継電器の使用が推奨されている。
絶縁協調
絶縁協調とは、電力系統各部の機器、設備の絶縁の強さに関して、技術上、経済上並びに運用上からみて最も合理的な状態になるように協調を図ることをいう。
雷過電圧を例にとり、500 kV 送変電設備の絶縁協調を送電設備と変電設備に分けて説明する。
送電設備の絶縁協調
送電線の耐雷設計として最も一般的に行われているのは、電力線に直撃雷が侵入しないように送電線を遮へいする架空地線の布設である。
架空地線を布設しても、電撃電流の波高値が小さな雷では遮へい失敗し、電力線へ直接侵入することがある。このとき発生する過電圧が大きいとアークホーンでフラッシオーバする(正フラッシオーバ)。また、架空地線や鉄塔へ雷撃があった場合、雷電流が大きいとアークホーンで逆フラッシオーバが発生し、電力線に雷が侵入する。
雷によるフラッシオーバに伴う送電線事故は再送電が可能なことが多いため、ある程度の事故(フラッシオーバ)率は許容して、送電設備の小型化を図り、建設コストの上昇を抑えている。500kV 送電線では、架空地線を一般的に2条布設し、また架空地線を電力線より外側に布設し負の遮へい角とし、下位電圧よりフラッシオーバを減らし、送電線事故を減少させている。
遮へい失敗や鉄塔部での逆フラッシオーバにより電力線に侵入した雷電流は、アークホーンにより制限されるものの、電力線を伝搬して変電所に侵入し、極めて高い過電圧を発生させる。この過電圧については、以下に示すように変電設備側で対策を実施している。
変電設備の絶縁協調
変電所の耐雷設計では一般に、変電所近傍の鉄塔への落雷による逆フラッシオーバによる近接雷と電力線を伝搬してくる遠方雷を考慮する。これらの雷過電圧に耐える絶縁強度を機器(変圧器や開閉器)にもたせることは経済的ではないため、変電所内に避雷器を設置し、最適位置に配置することにより雷過電圧を抑制し、効果的な絶縁協調を図っている。
避雷器の設置により過電圧抑制のための機器代は増加するものの、過電圧を確実に抑制できるため、低減した絶縁強度の変圧器や開閉器が採用でき、主要機器代が減少し、技術上、経済上並びに運用上から合理的な設計にすることができる。
500 kV の GIS 変電所を例にとると、想定雷撃電流は 150 kA を採用している。GIS 母線の広がりが下位電圧の母線より大きいことから、避雷器は線路引込口及び変圧器近傍に設置することが一般的である。雷インパルス試験電圧は、変圧器は 1 300 kV、GIS は 1 425 kV を採用している。
以上のように、送変電設備を一貫した耐雷設計が行われている。
配電設備の絶縁協調
雷過電圧を例にとり、配電設備と送変電設備との絶縁協調の違いについて説明する。
配電設備は送電設備と異なり、絶縁レベルが相対的に低く、機器が分散配置されていることから、雷事故を軽減するためには耐雷対策に十分な配慮を要する。雷過電圧の発生要因は配電線への直撃雷と、近隣の落雷により発生する強い電磁界による誘導雷の2種類がある。後者による発生電圧は数百キロボルト程度にとどまり、送電線では脅威にならない。
配電設備の耐雷対策としては、架空地線で電力線と機器とを遮へいする方法と、侵入した雷による過電圧抑制や機器保護のため避雷器やアークホーンを用いる方法があり、これらを組合わせることが有効である。開閉器、変圧器などの主要な機器は、避雷器を内蔵したり、極力近傍に設置して保護している。線路も保護範囲を考慮して避雷器を適切に設置したり、電線や碍子の雷による被害を防止するために、アークホーンを設置して保護している。
計器用変成器
(1)変流器は、一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。
(2)変流器は、二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。
(3)変流器は、通電中に二次側が解放されると変流器に異常電圧が発生し、絶縁が破壊される危険性がある。
(4)変流器は、一次電流が一定でも貫通ターン数により変流比は変化するので、電流計の選択には注意が必要になる。
(5)変流器の通電中に、電流計をやむを得ず交換する場合は、二次側端子を短絡して交換し、その後に短絡を外す。
調相設備
- 電力系統において、地中ケーブルの拡大などによる静電容量の増大に伴い、軽負荷時に受電端電圧が送電端電圧より上昇するフェランチ現象が発生することがある。この対策として分路リアクトル}\)を投入し、電圧及び無効電力調整を行う。
- 配電系統において、力率改善、電圧降下の抑制、電力損失の低減などを目的に並列コンデンサが使われている。力率改善のために使用する場合、負荷の有効電力をP[kW]、力率を\(\cos\theta_1\)とし、コンデンサ設置の前後で有効電力が一定であるとき、力率を\(\cos\theta_2\)に改善するために必要な並列コンデンサの容量は\(P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\)[kvar]となる。
電力系統の電力損失
電力系統における電力損失(発電所で発生した電力が、需要家に供給されるまでの間に発電所、変電所及び送電線や配電線でその一部が失われること)に関して、電力損失を発電所所内電力と送変配電設備に分け、それぞれの損失を構成する内容は以下。なお、発電所は汽力を原動力とする火力発電所とし、直流送電は想定しない。
- 発電所所内電力
- 発電のために使用する動力、照明、電熱などをいう。
火力発電所では、冷却水循環やボイラ給水、送風などのほか、排煙脱硫装置や石炭灰の処理などの動力が必要になる場合もある。
- 発電のために使用する動力、照明、電熱などをいう。
- 送変配電設備の電力損失
- 送電線路・変電所・配電線路中で消費される銅損や鉄損、その他の電力損失であり、潮流や力率などによって変動する。
電力系統の電力損失では一番大きい。
送配電線の抵抗損(オーム損)がメインで、変圧器では鉄損や銅損が発生する。超高圧送電線ではコロナ損、地中送電線では誘電体損やシース損がある。
- 送電線路・変電所・配電線路中で消費される銅損や鉄損、その他の電力損失であり、潮流や力率などによって変動する。
2017年においての水力発電所所内電力の所内比率(発電電力量に対する所内電力量の割合)、及び送変配電設備の損失率について、全国平均実績値[%]はそれぞれ、
水力発電所所内比率の全国平均実績値 1%
送変配電設備の損失率の全国平均実績値 5%
発電所を除く電力系統における電力損失軽減対策について以下が挙げられる。
- 潮流改善
電力系統間をつなぐ連系送配電線路を新設するなどして各電力系統を流れる電力潮流を改善し、電力損失の軽減を図る。 - 過負荷解消
過負荷傾向にある送配電線路に対し新たに送配電線路を新設・増設するなどにより過負荷を解消し、電力損失の軽減を図る。 - 力率改善
遅れ力率で値が悪いと電流が増え電力損失が増加することから、電力コンデンサを設置して遅れの無効電力を打ち消し電力損失の軽減を図る。 - 電圧格上げ
電力損失は電流と抵抗によるものであり、送電線や高圧配電線の格上げ(上位電圧への移行)により電流値を抑え電力損失の軽減を図る。 - 損失軽減機器・機材・構造の採用
低損失変圧器・低損失電線など、高効率・低損失の電力機器・機材・構造を採用し電力損失の軽減を図る。
電線路の絶縁性能の試験方法
「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に基づき、絶縁性能を確認するために現場で行う試験について、低圧の電線路と高圧以上の電線路における試験方法は別に定められている。
低圧電線路の絶縁性能は絶縁抵抗の値で規定され、絶縁抵抗測定により確認する。これに対し、高圧以上の電線路の絶縁性能は、試験電圧と試験時間とによって定められている絶縁耐力試験により確認する。
絶縁抵抗測定は、試験しようとする電線路の電線相互間及び電路と大地との絶縁抵抗が、規定値以上であることを確認する。絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電線路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、規定値以下であることを確認する。
電線にケーブルを使用する高圧又は特別高圧の交流の電線路に関し、直流による試験が認められている。その考え方及び方法は以下。
長距離の電力ケーブルは対地静電容量が大きく、交流試験では所要電源容量、試験設備が大きくなり、その実施が困難である場合が多いため、比較的容易に実施できる直流での耐圧試験を行うことが認められている。
交流試験の試験電圧の2倍の直流電圧を、電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐えられることを確認する方法である。
絶縁耐力試験
電気工作物の保全
電気工作物の保全目的
電気工作物の事故等の発生により、公共の安全や電力の安定供給等が脅かされるので、常に法令で定める技術基準に適合するよう、その性能等を維持すると共に、事故の未然防止を図ることが必要であり、それが保全の目的となる。
事後保全(CM:Corrective Maintenance)
故障停止又は著しい性能低下に至ってから修理を行う保全方式であり、通常事後保全と緊急保全とに管理上、分類できる。
予防保全(PM:Preventive Maintenance)
定期保全方式
従来の経験又は、その電気工作物の特性から一定期間の周期を定めて点検を行い、定期的に分解・清掃又は部品交換や補修を行い、突発事故を未然に防ぐ保全方式をいう。
予知保全(状態監視保全)方式
① 機器・設備の劣化状態を把握できるので、無駄な交換が不要となり、保全費用を低減できる。
② 機器・設備の異常兆候の早期発見や予測などが可能であり、機器の故障やシステム停止を未然に防止できる。
③ 機器の劣化による機能低下を検知することができ、システムの機能及び性能の低下を防止できる。
高圧受電設備の保守管理
- 高圧受電設備の場合、電力会社の変電所からの配線線に複数の需要家が連なっており、自己の事故によって、配電線路の上位の変電所で遮断することになると他の需要家に影響を及ぼすことになる。このような事故を波及事故というが、受電設備の主遮断装置から見て負荷側の事故に対しては、十分な遮断容量と保護リレーの保護協調が重要であり、主遮断装置から電源側に対しては、入念な点検による故障要因の事前発見、予防が大切になる。
- 波及事故の発生個所は主遮断装置及びその電源側に多く、具体的なものとしては、主遮断装置の他、高圧開閉器、高圧引込ケーブル、断路器などがある。
- なお、PF・S形は、主遮断装置として高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器を組み合わせて保護するものである。
高圧受電設備の保護
高圧受電設備の主遮断装置と保護の方式について、受電設備容量 300kV・A を区切りにして分かれる。
受電設備容量 300kV・A 以下の主遮断装置には、高圧限流ヒューズ(PF)と高圧交流負荷開閉器(LBS又はS)を組み合わせた方式が主に用いられる。
地絡事故が発生したときは地絡リレー(GR)、地絡過電流リレー(OCGR)又は地絡方向リレー(DGR)で検出し開閉器をトリップさせ、短絡事故のときは、短絡電流が大電流であるため PF で遮断する。
300kV・A 以上の主遮断装置には、真空遮断器(VCB)などの遮断器(CB)と地絡・短絡などのリレーを組み合わせた方式が主に用いられる。
地絡、短絡などの事故、あるいは過負荷が発生したときは、GR 又は DGR、過電流リレー(OCR)または地絡過電流リレー(OCGR)などで検出し CB を遮断させ設備を保護する。
地絡方向リレー(DGR)と地絡リレー(GR)の地絡事故に対する動作原理の違いは以下。
DGRは、零相電圧検出器(ZPD)で零相電圧(V₀)、零相変流器(ZCT)で零相電流(I₀)を同時に検出する。また、V₀とI₀の位相から地絡電流の方向を判別することで、地絡事故が自家用構内側か構外側かを区別している。
GRは、ZCTのみしか使用していないため、一定以上のI₀が流れた場合に地絡事故の判定をする。零相電流の値のみのため、誤動作の可能性がある。
油入変圧器の絶縁材
油入変圧器の内部絶縁には、絶縁油と絶縁紙(クラフト紙)などのセルロース系絶縁材料が使用されている。これら絶縁材料について次の問に答えよ。
- 不燃性・難燃性などの防災性や環境適合性の観点から、鉱油以外の絶縁媒体を使用した油入変圧器が実用化されている。鉱油以外の絶縁媒体は以下。
- シリコーン油
- 合成エステル油
- 植物油
- 絶縁紙の絶縁特性を向上させる方法の一つとして、油浸して気密度を上げる方法があるが、その他の方法は以下。
- 絶縁紙の密度を上げる。
- 絶縁紙の含有水分量を減らす。
油入変圧器の絶縁劣化診断
油入変圧器の絶縁劣化の原因
- 絶縁油には一般に鉱油が使用されているが、絶縁油が吸湿したり、空気に長時間さらされると絶縁性能が低下する。この場合の絶縁油の絶縁特性を確認する診断項目と絶縁性能低下との関係は以下。
- 絶縁破壊電圧
酸化や水分量の増加、油中微粒子などにより絶縁油が劣化すると絶縁破壊電圧が低下する。 - 全酸価
絶縁油の酸化劣化により有機酸が生成され全酸価が増加すると、絶縁性能が低下する。 - 体積抵抗率
絶縁油が劣化するとイオン性の物質が増加し体積抵抗率が減少し、絶縁性能が低下する。 - 誘電正接(tanδでも正解)
絶縁油が劣化するとイオン性の物質を生成するため誘電体損が増加し、絶縁性能が低下する。 - 水分量(油中水分量でも正解)
絶縁油中の水分量が増加すると絶縁性能が低下する。
- 絶縁破壊電圧
絶縁油の劣化
絶縁油に空気中の水分や酸素が溶け込むと、絶縁破壊電圧の低下、全酸価(酸価、酸価度)の上昇などにより劣化が進行する。
- 対応する絶縁劣化診断試験
- 絶縁破壊電圧試験
- 全酸価試験
絶縁紙の劣化
油入変圧器の長期間の運転による発熱により絶縁紙の平均重合度が低下すると引張り強さが低下し劣化が進行する。
- 対応する絶縁劣化診断試験
- 油中ガス分析試験
内部絶縁材料(絶縁油、絶縁紙、プレスボード等)の劣化
内部異常時の局部的な発熱や、長期間の運転による発熱で、絶縁材料が熱分解し劣化が進行する。
- 対応する絶縁劣化診断試験
- 油中フルフラール分析試験
各種絶縁劣化診断試験
絶縁破壊電圧試験
- 劣化診断の原理
- 商用周波数における絶縁油の絶縁破壊電圧を測定し、劣化度を推定する。
- 劣化診断試験の実施方法例
- 試料を試験容器に満たし、相対する球電極間に商用周波数の試験電圧を印加し、一定の割合で上昇させ絶縁破壊電圧を測定する。
全酸価試験
- 劣化診断の原理
- 絶縁油に含まれる全酸価を測定し劣化度を推定する。全酸価とは、絶縁油 1 g 中に含まれる全酸性成分を中和するのに要する水酸化カリウムの mg 数をいう。
- 劣化診断試験の実施方法例
- 試料をトルエン・エタノールの混合溶剤に溶かし、アルカリブルー 6B を指示薬として水酸化カリウムの標準エタノール溶液で滴定する。
油中ガス分析試験
- 劣化診断の原理
- 内部絶縁材料が熱分解すると、絶縁材料や異常の種類によって特有のガスが発生し、一部は油中に溶解する。この発生ガスを分析し、内部異常や劣化度を推定する。
- 劣化診断試験の実施方法例
- 試料に溶け込んだ発生ガスをガスクロマトグラフにより分析する。
油中フルフラール分析試験
- 劣化診断の原理
- 絶縁紙のセルロース分子が劣化分解すると、フルフラールなどの生成物が発生する。フルフラールは、沸点が約162℃の液体であるため、常温で絶縁油に溶解する。絶縁紙の平均重合度残存率及び引張り強さと一定の関係があるフルフラール量を測定し、劣化度を推定する。
- 劣化診断試験の実施方法例
- 試料に溶け込んだフルフラールを液体クロマトグラフにより分析する。
- 自家用需要家が絶縁油の保守、点検のために行う試験には、絶縁耐力試験及び酸価度試験が一般に実施されている。
- 絶縁油、特に変圧器油は、使用中に次第に劣化して酸価が上がり、抵抗率や耐圧が下がるなどの諸性能が低下し、ついには泥状のスラッジができるようになる。
- 変圧器油劣化の主原因は、油と接触する空気が油中に溶け込み、その中の酸素による酸化であって、この酸化反応は変圧器の運転による温度の上昇によって特に促進される。そのほか、金属、絶縁ワニス、光線なども酸化を促進し、劣化生成物のうちにも反応を促進するものが数多くある。
- 絶縁油は、油入変圧器や油入コンデンサなどの電気機器に広く使用されており、その主な役割は機器の絶縁と冷却である。油入機器の内部で異常過熱や絶縁劣化が生じると、絶縁油から発生した分解ガスや絶縁物の劣化生成物が絶縁油に溶け込み、絶縁油の化学的特性に変化が生じてくる。絶縁油の保守管理は、油入機器の絶縁状態を把握するとともに機器の性能を長く維持するために重要なことである。
- 油入変圧器を運転すると温度が変化し外気との間で呼吸作用が行われる。その際、ブリーザ不良、パッキング劣化、シール部の締付不良、外装タンクの腐食などによる気密不良があると、絶縁油に空気中の酸素や水分が混入する。絶縁油は油中に酸素や水分が存在すると、変圧器内部の鉄や銅の裸金属に接触している状態で運転中の温度上昇により、酸化反応が促進され酸性有機物質の総量(酸価)が増大する。酸価が増大すると絶縁油と金属やコイル絶縁物が化合しスラッジ(絶縁油の劣化によって生じる泥状物質)が生成される。これがコイル絶縁物、鉄心、放熱面に付着すると放熱機能が低下し、温度上昇が著しくなり絶縁物の熱劣化が加速される。
- 絶縁劣化した状態で油入変圧器の運転を続けいていると、過電圧などによって部分放電が発生し、外部からのサージや外部短絡時の電気的又は機械的ストレスで絶縁破壊に至るおそれがある。また、絶縁油自体も劣化生成物の溶解によって吸水性を増し、絶縁抵抗の低下やtanδの増加などの絶縁特性が低下する。
- 絶縁油は定期的に試験を行って劣化状況を確認する必要があり、試験項目としては、絶縁破壊電圧試験、酸価試験、水分試験などがある。
油中ガス分析
変圧器の異常診断手法として油中ガス分析が用いられている。油中ガス分析は可燃性ガスの量や組成比などから内部異常の有無・様相を診断する手法である。油中ガス分析による異常診断方法及び最終的な処置を決定するための総合診断について以下に述べる。
(1)過熱時に発生する特徴的なガスと、その発生ガスの組成比などから推定できる過熱の様相。
過熱時に発生する特徴的なガスとしてエチレン\((C_2H_4)\)とエタン\((C_2H_6)\)が挙げられる。
過熱レベル(高温過熱・低温過熱)により発生ガスの成分が変化し、高温過熱ではエチレンが、低温過熱ではエタンが多く発生する。また、組成比などから過熱部位(巻線部・金属部)の推定を行うことができる。
過熱時発生するガスに、メタン\((CH_4)\)、一酸化炭素\((CO)\)、二酸化炭素\((CO_2)\)などもある。
(2)放電を伴う内部異常時に発生する特徴的なガス、内部異常時以外にもこのガスが発生する原因。
放電時に発生する特徴的なガスとしてアセチレン\((C_2H_2)\)、水素\((H_2)\)が挙げられる。アセチレンは絶縁油から発生する分解ガスのうち、アーク放電など特に高温時に発生するものである。
水素は経年劣化でも発生する一方、アセチレンは微量であっても検出された場合は内部異常の可能性が高い。
アセチレンはLTC(負荷時タップ切替器)動作時に切換開閉器室内の絶縁油が分解することでも発生することから、LTC内の絶縁油が変圧器本体タンクへ混入すると内部異常と誤診断されるおそれがあるため、注意が必要である。
(3)油中ガス分析で内部異常と診断された場合、総合診断を行うために実施すべき試験・点検・調査事項並びに、最終的に決定する処置内容。
電気的試験(巻線抵抗、部分放電測定など)、外部一般点検(放圧管の動作、タンクの変形など)、運転履歴・改修履歴の調査(過負荷運転など)などの項目を総合して、変圧器の運転継続可否、内部点検・改修の要否などの最終的な処置を決定する。
大容量変電機器の品質確保
- 大容量変電機器の品質を確保するために、輸送及び現地据付けに関して、設計時に配慮する事項。
- 大容量変圧器及び大容量 GIS に共通して配慮する事項
工場で試験を終えた変電機器は、必要に応じて輸送のための分解、梱包を行ってから、現地へ輸送される。そして現地ではこれらの分解された機器を組み立て、絶縁媒体の封入を行い、正規状態となる。大容量変電機器の設計に際して、輸送においては、輸送単位が機器一体輸送、又は分解数を極小化するように配慮されており、品質向上に役立っている。また、現地据付けにおいては、現地作業の範囲を極小化、単純化し、施工不良の発生を防止するように設計されている。 - 大容量変圧器及び大容量 GIS に個別に配慮する事項
➀変圧器では、リードの接続においては、工場製造時に取り付けた羽子板端子構造によるボルト締結として、現地でのリード切断などを行わない構造としていること、冷却部取り付け部の接続では、取り付け部のバルブを本体側のフランジに取り付けたまま、冷却器を取り外せる構造により分解、輸送時の防水、防塵効果を高めることが上げられる。
➁ GIS では、通電部の通電接触子を用い、導体部に、はめあい構造、ボルト締結といった簡易な接続方法を採用し、複雑な作業を伴わず、確実な接続ができるように配慮されている。一方、タンク接続においては、フランジ部の防水構造化、吸着剤取り付けによる防湿対策がなされている。また金属異物の発生しにくいはめ合い構造による異物対策がなされている場合もある。
- 大容量変圧器及び大容量 GIS に共通して配慮する事項
- 現地据付けにおいて品質管理に必要な事項を、➀作業環境、➁絶縁物の吸湿防止、➂異物混入防止に関して、機器ごとにそれぞれ説明する。
- 大容量変圧器
➀作業環境:タンク内に塵埃や異物が混入しないために周囲に隔壁や蓋いを設置するなどの防塵措置を施すと共に、作業場周辺に散水を行うなどの作業環境を整備し、場合により粉塵計を使用して防塵管理を行う。
➁吸湿防止:タンク内作業時における絶縁物の吸湿を防止するために、絶縁物の露出時間を管理すると共に、作業に使用する乾燥空気の湿度とタンクの内部湿度を管理する。現地作業中に吸湿した水分を熱湯噴霧循環により乾燥させ、絶縁物表面部分の水分量を基準値以下にする。高真空下(0.1 から 3 [Torr] )で脱気装置を通して脱気ろ過した絶縁油を注油する。
➂異物混入防止:真空脱気注油後、さらに絶縁油中の微小な塵埃を除去し、脱気度を向上させるために、タンク内の絶縁油を真空脱気装置を通して脱気ろ過循環する。 - 大容量GIS
➀作業環境:現地接続部の組み立て後の品質は、作業環境の影響を受けやすい。雨天時の作業を回避すると共に、湿度、風速 及び塵埃を基準値以下に確保する必要がある。(湿度 80[%] 以下、風速 5 [m/s] 以下、塵埃は 20 [カウント/min] 以下)
➁吸湿防止:組み立て中では、所定の防水処理を行い、吸着剤の放置時間は30分以内とする。
➂異物混入防止:作業中はフランジ面への保護カバー取り付けや、Oリングの傷、異物のないことの確認に留意し、防塵フェンスや防塵ハウスを適用し、防塵に配慮して接続作業を行う。ガス処理を行う前に導体接続部の目視確認を行い、真空掃除機などを用いて、タンク内部を清掃後、吸着剤を取り付ける。
- 大容量変圧器
電磁ノイズ
近年における電気電子技術の急速な進歩に伴い、電磁障害の防止は、現代の電気施設管理にとって重要なテーマである。
電磁障害を防止するためには、電磁ノイズを発生及び被害の両面から考えていく必要がある。
- 次の表は、電気の品質に関係が深い4種類の電磁ノイズについてまとめたものである。
- 瞬時電圧低下(瞬低、電圧ディップ)
<意味>数サイクルから数秒の短時間で回復するような、電力系統のある1点における突然の電圧低下。電圧の低下は、その点を含む電力系統の周辺に及ぶ
<主な発生要因>架空送電線等の地絡、短絡事故。(架空送配電線への落雷)
<主な被害機器>- コンピュータ
- 汎用インバータ
- 電磁接触器
- 降圧放電灯
- 高調波電流
<意味>基本は周波数成分以外の周波数成分の電流
<主な発生要因>パワーエレクトロニクス適用機器など、非線形特性をもつ機器
<主な被害機器>進相コンデンサ装置。(進相コンデンサ本体又は直列リアクトル) - フリッカ
<意味>光度又はスペクトル分布が時間とともに変動する光の刺激によって誘起される視覚上の不安定さに対する印象
<主な発生要因>アーク炉。(大型溶接機)
<主な被害機器>白熱灯、蛍光灯 - 電圧不平衡
<意味>三相系統において、相電圧の実効値又は隣り合う期間の位相角が全て等しいという訳ではない状態
<主な発生要因>大容量単相負荷配置のアンバランス
<主な被害機器>同期発電機、誘導電動機
- 瞬時電圧低下(瞬低、電圧ディップ)
- 電磁両立性(EMC : Electromagnetic Compatibility)とは、装置またはシステムの存在する環境において、許容できないような電磁妨害をいかなるものに対しても与えず、かつ、その電磁環境において満足に機能するための装置又はシステムの能力。
高調波・フリッカ対策
高調波抑制対策ガイドライン
「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」では需要家から系統に流出する高調波電流の上限値が示されており、6.6kV系統への第5次高調波の流出電流上限値は契約電力1kW当たり3.5mAとなっている。
ダイオード及びサイリスタを用いた\(\fbox{非線形}\)負荷は、各種次数の高調波電流を発生する。電気設備及び機器に及ぼす高調波の影響は、以下のように分類される。
- 機器への高調波電流の流入による異音、過熱、振動、焼損など
- 機器への高調波電圧の印加による誤制御、誤動作など
このような影響が生じる場合があることから、配電系統の6.6kV母線における高調波電圧総合ひずみ率の管理目標値を5%、特別高圧系統の高調波電圧総合ひずみ率の管理目標値を\(\fbox{3%}\)とし、これを維持するため、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」による高調波電流抑制のための技術要件が定められている。
高調波電流の抑制対策は、機器から発生する高調波電流そのものを低減する方法と、機器から発生した高調波電流を需要家内の設備に\(\fbox{分流}\)させ、外部に流出する量を低減する方法の2種類がある。
具体的には、前者においては高調波発生源である電力変換装置の\(\fbox{多パルス化}\)、後者においては需要家内への受動\(\fbox{フィルタ}\)などの設置といった方法がある。
配電系統における電気の品質確保の一環として、電圧を適正に管理する必要がある。管理の対象としては、以下に示す電圧の値、フリッカ、高周波などが挙げられる。
- 供給電圧の値は、需要家で使用する機器の性能に大きな影響を与えるため、電気事業法施行規則で供給地点での電圧を次のように定めている。
電気事業法施行規則 第三十八条(電圧及び周波数の値)
・標準電圧100Vの場合:101±6V
・標準電圧200Vの場合:202±\(\fbox{(ト)20}\)V
全ての需要家に対しこの範囲で供給するための対策として、変電所の送り出し電圧の調整や、配電線途中での\(\fbox{(ル)線路電圧調整器}\)の設置などが挙げられる。 - 配電線に\(\fbox{(ヨ)アーク炉}\)、溶接機、太陽光発電用パワーコンディショナ(PCS)などが接続されると、\(\fbox{(カ)起動}\)時や運転中の負荷変動時、PCSの単独運転検出機能動作時などに線路電圧が変動し、照明の明るさにちらつき(フリッカ)が生じることがある。この抑制対策は基本的に発生源である機器側で行われるが、系統側での対策としては、電圧降下を低減するような電線サイズの設定、変圧器・配電線の専用化などが考えられる。
- 整流器、\(\fbox{(ヨ)アーク炉}\)などの、非線形特性をもった負荷に電力を供給した場合、それらの機器から高調波が発生し、通信線への誘導障害、\(\fbox{(ホ)コンデンサ}\)への過電流、電気機器の誤動作などが発生するおそれがある。これらを防止するために、我が国では、系統電圧の総合ひずみ率が高調波環境目標レベル(6.6kV配電系統で5%、特別高圧系統で3%)を超えないよう、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」によって、発生源である機器側における高調波電流の限度値が定められている。
高調波・フリッカ対策
配電系統の電力品質や需要家に影響を与える恐れのある高調波やフリッカ現象の対策について述べる。
- 需要家に設置される進相コンデンサは、JIS C 4902 で直列リアクトルとともに使用することが標準として規定されている。直列リアクトルを設置する理由。
- 直列リアクトルは、高調波に対して進相コンデンサ設備の回路を誘導性にし、進相コンデンサのキャパシタンスと系統の変圧器や線路のリアクタンスとの共振による高調波電流の拡大を防止する。
- コンデンサ投入時の突入電流や異常電圧発生を抑制する。
- 高調波対策設備の一つである LC フィルタについて高調波抑制の原理と、設置に当たり留意すべき点。
【高調波抑制の原理】
LCフィルタは、コンデンサ、リアクトルといった受動(パッシブ)素子を組み合わせて、特定の周波数又は周波数領域で低インピーダンスとなる分路を構成し、高調波電流を吸収する。
【設置に当たり留意すべき点】
下記のような解答が、いずれか2項目記載されていればよい。- 無負荷時に母線電圧が上昇するため、高調波発生機器の停止時は進み力率を避けるため、LCフィルタを開放することが望ましい。
- 系統反共振点での高調波不安定現象
LCフィルタは、発生する高調波次数に対応した分路を組み合わせるため、分路の次数や低次側に電力系統インピーダンスとの共振点が現れる。共振している次数の高調波が存在すると、その高調波電流が増加して変換装置が運転不能となるため留意する必要がある。 - 遮断器の選定
LCフィルタは、進相コンデンサに比べて高調波電流の流入量が多いため、遮断後の回復電圧が大きくなる。このため、遮断直後の過渡回復電圧抑制用サージアブソーバの設置や1ランク上位の電圧定格をもった遮断器の採用などが必要となる。 - LCフィルタの電流耐量
LCフィルタは電力系統内で第 n 次高調波に対して短絡回路を形成するため、電流耐量に留意する必要がある。 - 励磁突入電流の引き込みが大きい場合には、耐量向上又は運用上の対策が必要となる。
- 同調フィルタの並設時は、それぞれのLCフィルタの同調点をずらしてフィルタインピーダンスを大きくする。
- フリッカの対策法について。
- 需要家側の対策
- 静止形無効電力補償装置(SVC、SVG)等を施設する。
- アーク電流が不安定な交流アーク炉に代え、安定した電流が得られる直流アーク炉を採用する。
- 一次側に直列過飽和リアクトルを接続する。
- 供給側の対策
- 変動負荷を専用線あるいは専用変圧器により供給する。
- 高圧配電線の昇圧、電線の太線化など電源側インピーダンスの低減を図る。
- 需要家側の対策
電力系統の構成
- 送電線路の相互連系を容易にすることや、機器の規格化などを考慮し、送電電圧は数種類の標準電圧に統一されている。我が国の標準電圧は電気学会・電気規格調査会(JEC)で定められており、\(\fbox{公称電圧}\)と最高電圧の2種類がある。例えば、\(\fbox{公称電圧}\)が66kVの場合は、最高電圧は69kVとなっている。なお、送電線路の電圧としてこの標準電圧を採用する場合、\(\fbox{公称電圧}\)が電気設備技術基準の「使用電圧」となる。
- 交流送電線の送電容量は、電線の許容最高温度に対する許容電流だけでは決まらず、こう長が長いと送電容量が小さくなる。送電線のこう長が長くなると\(\fbox{安定度}\)から送電容量が制限されるためである。
- 架空送電線路の電力損失の主なものに、抵抗損と\(\fbox{コロナ損}\)がある。\(\fbox{コロナ損}\)は、送電線に高電圧を加えたとき、周囲の空気に対する電線表面の電位の傾きがある程度以上になると発生する局部放電によるものである。
- 架空送電線の事故は、\(\fbox{雷によるアーク事故}\)が多く、設備の損壊を伴う永久故障は少ない。このため線路の両端を開いて短時間無電圧の状態におき、その後再び両端を閉路すれば元通り送電できることが多い。このことを利用して自動再閉路方式が多く採用されている。
- 配電方式のうち、都市部などで採用されることがあるものに、次の方式がある。
複数の22kV配電線から分岐線をT分岐で引き込み、それぞれ受電用断路器を経てネットワーク変圧器に接続し、各低圧二次側はネットワークプロテクタを経て並列に接続してネットワーク母線を構成する。本方式では、低圧側は同一ビル内の母線に限定される。
この方式は\(\fbox{スポットネットワーク方式}\)と呼ばれている。
架空電線路
架空送電線の保守
架空送電線は、山間地の水力発電所、沿岸部の火力・原子力発電所から需要地点に至るまで、山岳部、平野部、沿岸部と様々な立地条件の中を経過しており、雨や風、雪や雷等自然現象に起因する\(\fbox{事故}\)が多いだけではなく、鳥獣や樹木の接触、架空送電線付近で行われる工事用の重機や他工作物の接近等による障害も多い。
架空送電線の保守の目的は、基本的には、電力の\(\fbox{安定供給}\)と設備の合理的な維持であり、目的達成のために必要な業務は、大別すると、巡視、\(\fbox{点検}\)、補修作業、事故処理、渉外業務に分類できる。
巡視は、保守の目的を達成するために必要な業務の一つであり、架空送電線の状況を常に的確に把握するため、設備の外観等を見回り、\(\fbox{事故}\)の原因となる障害箇所を事前に発見し、その\(\fbox{未然防止}\)を図るとともに、設備の補修に必要なデータその他の資料を集めるための業務である。
巡視には幾つかの種類があるが、一般的に定期巡視のうち特定巡視と呼ばれるものは、市街地やその周辺など架空送電線の経過地の状況変化が著しく、架空送電線に障害を及ぼすおそれのある工作物の新増設や土地造成に伴う異常等を早期に発見するため、\(\fbox{区間}\)を定めて行う巡視をいう。
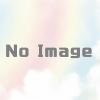
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません