変電所の学習帳
目次
変電所の役割
変電所とは、発電所から送電線によって送られてきた電気の電圧・電流を変成したり、電気の集中・配分を行う。その他、電気の質をよくするために電圧・電力の調整や無効電力の配分制御を行う。
変電所は、用途の面から、送電用変電所、配電用変電所などに分類されるが、東日本と西日本の間の連系に用いられる周波数変換所や北海道と本州の連系に用いられる交直変換所も変電所の一種として分類されることがある。
電力系統における変電所の役割と機能
- 主に送電効率向上のための昇圧や需要家が必要とする電圧への降圧を行う。構外から送られる電気を、変圧器やその他の電気機械器具により変成し、変成した電気を構外に送る。
- 送電線路で短絡や地絡事故が発生したとき、保護継電器により事故を検出し、遮断器にて事故回線を系統から切り離し、事故の波及を防ぐ系統保護の役割を担う。
- 送変電設備の局部的な過負荷運転を避けるため、開閉装置により系統切換を行って電力潮流を調整する。
- 無効電力調整のための調相設備を有し、重負荷時には電力用コンデンサを投入し、軽負荷時には分路リアクトルを投入して、電圧をほぼ一定に保持する。
- 負荷変化に伴う供給電圧の変化時に、負荷時タップ切換変圧器等により電圧を調整する。
変電所の主な構成設備
開閉設備
開閉設備には、主に以下のような種類がある。
- 消弧装置を持たない断路器
- 主回路の接地を目的とする接地開閉器
- 負荷電流や故障電流を遮断するための遮断器
それぞれの開閉設備について詳しくはこちら。
変圧器
変圧器の結線方式
変圧器の一次側、二次側の結線にY結線及び△結線を用いる方式は、結線の組合せにより四つのパターンがある。
このうち、△-△結線はひずみ波の原因となる励磁電流の第3高調波が還流し、吸収される効果が得られるが、一方で中性点の接地が必要となる場合は適さない。
Y-Y結線は一次側、二次側とも中性点接地が可能という特徴を有する。△-Y結線及びY-△結線は第3高調波の還流回路があり、一次側若しくは二次側の中性点接地が可能である。
△-Y結線は昇圧用に、Y-△結線は降圧用に用いられることが多い。
特別高圧系統では変圧器中性点を各種の方法で接地することから、Y-Y結線の変圧器が用いられるが、第3高調波の還流の効果を得る狙いから△結線を用いた三次巻線を採用していることが多い。
短絡電流抑制のための変圧器仕様
1. 系統の大容量化・集中化により増大する短絡電流を抑制するために、変圧器の仕様及び変圧器の機器設計で考慮すべき事項。
➀変圧器の仕様
短絡電流を抑制するために、変圧器のインピーダンスを大きく設定する。
変圧器のインピーダンスを大きくすれば、電圧変動率が大きくなり、系統安定度が悪くなる方向にいくので、システムコーディネーションの観点から、系統と機器のバランスを考え、変圧器のインピーダンス値を選定している。
例えば、500kV 変圧器で一般的なインピーダンスが 14 [%] に対して、高インピーダンスでは 23 [%] が用いられることが多い。
➁変圧器の機器設計で考慮すべき事項
高いインピーダンスにするために、巻回数の増大、巻線径増大が行われる。
SF₆ ガス絶縁変圧器
近年、採用される例が増えている SF₆ ガスを循環して冷却する方式のガス絶縁変圧器に関して、油入変圧器との比較すると以下のような特徴を有する。
- 採用される場所とその理由
- 都市部の地下や屋内変電所:不燃性であることから、防火対策(防火設備や防火区画)が簡略化・合理化できる。
- 山岳地の水力発電所・変電所:油入変圧器の場合、漏油による河川汚染のリスクがあるが、それが回避できる。
- 変電所設計に対する構造上の長所
- 変圧器コンサベータや放圧装置が不要となるため、変圧器室の高さが低減でき建物建設コストの低減が図れる。
- GIS 等と直結し合理的な配置設計により建物面積の縮小化が可能となることから建物建設コストの低減が図れる。
- 保守面に対する構造上の長所
- SF₆ ガスは酸化劣化せず、吸湿呼吸器が不要なため、シリカゲル交換が不要となり、保守の省力化が可能となる。
- GIS 等と同様のガスシール構造を有し、技術蓄積による長期信頼性が期待でき、保守の省力化が可能となる。
- 300 MV・A 程度の大容量器における SF₆ ガスの冷却性能向上方策
SF₆ ガスは鉱油に比べ熱容量が小さいことから、以下に示す方法で冷却性能を向上させている。- SF₆ ガスの圧力を高めて、熱容量を増やす。
- 高耐熱絶縁材料により巻線の温度上昇限度を高める。
- 高ガス圧対応のガスブロアにより大量のガスを流す。
- 巻線内部のガス流路構成を解析により最適化し、大量のガスを均一に流す。
送電用変電所の油入変圧器の事故と対策
- 変圧器の事故のうち、巻線に関する事故様相について主なものは以下がある。
- 短絡:巻線の層間短絡
- 地絡:巻線と鉄心間の地絡
- 混触:高圧巻線と低圧巻線の混触
- 断線:巻線の断線
- 変圧器の流動帯電について、流動帯電により絶縁破壊に至る過程及び防止策については以下。
- 流動帯電は、大容量の導油式変圧器において、冷却のために絶縁油を循環させる際の摩擦により、固体絶縁物が負電荷の、絶縁油が正電荷の静電気で帯電する現象である。静電気の蓄積が絶縁油の耐圧値を超えると静電気放電が発生し、これが進展すると変圧器の絶縁破壊に至る。防止策として、絶縁油の流速を抑える、流動帯電防止剤を絶縁油に添加する、などの対策がとられる。
- 変圧器の保護に用いられる機械式保護リレーと電気式保護リレーについて、代表的なリレーと検出方式は以下。
- 機械式保護リレー
衝撃圧力リレーは、事故時に変圧器内部で発生する分解ガスによる内圧上昇を検出する。内圧上昇が早いほど検出することができる。(別解:ブッフホルツリレーは、事故によるガスの発生や油流増大を検出する。ただし、地震により誤動作する場合があるので、警報用とするなど注意を要する。) - 電気式保護リレー
比率差動リレーは、変圧器一次・二次の電流の換算値の差を常に比較し、小さい場合は正常、整定値より大きい場合は内部事故として検出する。差電流を動作量、通過電流を抑制量として比率特性を持たせることで、検出感度と誤動作防止に優れている。
- 機械式保護リレー
- 変圧器の事故を未然に防止するための外部診断方法の一つである油中ガス分析について、ガスが発生する過程及び判定方法は以下。
- 油中ガス分析は、変圧器の絶縁油を採油し、溶解している可燃性ガスをクロマトグラフによって測定することにより、内部状態を診断する方法である。変圧器の内部に異常が発生すると、高温により絶縁油や絶縁紙が油中ガスとして熱分解し、アセチレンなどのガスが発生する。そこで、油中ガス分析によって検出したガスの種類・発生量や、複数種類のガスの成分比を基準値と比較することにより、変圧器内部の異常の有無や様相を判定する。
- 変圧器の事故により火災や噴油が発生した際の、当該変圧器の周辺機器や変電所周辺環境への波及防止策は以下など。
- 消火対策
変圧器に火災が発生した場合に早期に消火するため、水噴霧などの固定消火装置や大形消火器を変圧器の周辺に設置し、火災発生時は自動的に起動する。 - 類焼防止対策
火災が発生した変圧器から、隣接する変圧器などへの類焼を防止するため、防火壁や防火水幕を設ける。 - 公害防止対策
変圧器事故による油流出や、変圧器火災の消火のための消火水が、変電所構外へ流出することを防止するため、油水流出防止せきや排油水槽を設ける。
- 消火対策
調相設備
調相設備は、電圧の調整と送電系統の安定度向上、送電線路の力率改善による電力損失の軽減を目的として設置される。これらの調相設備は送電回路に並列に接続され、変圧器の三次側や母線に設置される。
代表的なものには、静止器と呼ばれる、分路リアクトルや電力用コンデンサ、静止形無効電力補償装置(SVC)やなどがあり、回転機と呼ばれる同期調相機などがある。
調相設備について詳しくはこちら。
保護リレー/計器用変成器
保護リレーは電力系統に事故が発生したとき、事故を検出し、事故の位置や種類を識別して、事故箇所を系統から直ちに切り離す指令を出して遮断器を動作させる制御装置である。
計器用変成器は、計器用変圧器と変流器とに分けられ、高電圧あるいは大電流の回路から計器や保護継電器に必要な適切な電圧や電流を取り出すために設置される。
各種保護リレーや計器用変成器について詳しくはこちら。
需要家との保護協調
高圧需要家に構内事故が発生した場合、配電用変電所の保護リレーよりも先に同需要家の保護リレーが動作して遮断器に切り離し指令を出すことで、確実に事故を除去する。
各種限時特性
- 瞬時特性
ある電流以上では、瞬時に動作する特性。
- 定限時特性
ある電流以上では、電流の大きさに関わらず,一定時間で動作する特性。
- 反限時特性
電流値と動作時間が反比例関係となる特性で、電流値が大きければ早く動作する。
- 反限時定限時特性
反限時特性と定限時特性を合わせた特性。電流の小さい時は反限時特性,電流が大きくなると一定時間で動作する。
変電所の絶縁設計
電力系統には雷撃や系統運用における過渡現象などにより異常電圧が発生することがあり、電気施設の絶縁保護を目的に、変電所等に避雷器が設置される。近年は、特に、保護特性の優れた、直列ギャップを使用しない酸化亜鉛(ZnO)を主成分とした酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)が多く使用されている。
変電所の絶縁設計において、支配的な要素となるのが雷サージである。それらについての対策を行う必要がある。
変電所内への直撃雷の防止対策
変電所の変圧器や開閉器などの電力機器を雷の直撃に耐えるように絶縁することは極めて困難であるため、架空地線と避雷鉄塔による変電所内の遮へいと接地を施して、直撃雷の発生を防止する。
送電線からの侵入雷によるサージ低減対策
送電線からの侵入雷は、送電線への直撃雷、鉄塔フラッシオーバ、誘導雷によるものがある。いずれの場合も避雷器を変圧器付近、母線、線路引き込み口、あるいはそれらを組み合わせて接地して、雷サージの低減を行うことにより、保護する機器の絶縁レベルとの協調を行う。
変電所における避雷器の設置上の留意点及びその理由
- 避雷器は線路引込口や極力被保護機器近く設置する(約50m以下)ことが望ましく、距離があまり遠くなると被保護機器の端子に加わる異常電圧の値は避雷器の制限電圧に比べて高くなり、これを設置した効果がなくなる。
- 避雷器と大地間の接地線は極力接地抵抗(インピーダンス)を小さくし、高周波サージに対するインダクタンスを抑えることで、避雷器ー大地間の電圧上昇により保護レベルに影響をおよぼさないようにする。
酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)では、保護レベルと機器寿命の関係を定量的に示すのに、常時連続的に印加される電圧ストレスの大きさを示す課電率(通常、連続使用電圧/動作開始電圧)を用いる。そこで、課電率による保護レベル設定と機器寿命の関係については以下のようになる。
- 課電率を高くすることで、保護レベルを低く設定でき、絶縁設計の合理化が実現できるが、機器寿命が短くなるためこの経済バランスを考慮した仕様検討が必要となる。
低圧制御回路におけるケーブル施設時でのサージ低減対策
金属シース付き低圧制御ケーブルを採用しシースを接地する。低圧制御ケーブルを高電圧ケーブルから離すなどを行う。
低圧制御回路の絶縁設計
- 低圧制御回路の絶縁設計に配慮すべき電圧サージと、それらが制御回路へどのような経路で侵入するかについて、述べる。
経路:低圧制御回路の絶縁設計で配慮すべき異常電圧はサージ性電圧であり、雷サージ、主回路開閉サージ、直流回路開閉サージに分類され、下記のように低圧制御回路に侵入する。- 雷サージ:
・電気所の母線、接地線などに雷サージ電流が流れ、近接する制御ケーブルに誘導により移行する。
・計器用変成器の一次側雷サージ電圧、電流が二次回路に誘導により移行する。
・電気所の接地系に雷サージ電流が流入し、流入点の接地電位が上昇、近接する制御ケーブルに誘導により移行する。 - 主回路開閉サージ:
・遮断器や断路器の開閉で主回路に発生した開閉サージが計器用変成器の二次回路に誘導により移行する。
・GIS機器において、発生した開閉サージが接地電位を変動させ、近接する制御ケーブルに誘導により移行する。 - 直流回路開閉サージ:
・低圧制御回路である直流回路の容量性や誘導性の負荷を接点で開放するときに発生する。 - 地絡サージ:
・ケーブル系統における地絡事故初期のサージ電流が計器用変成器の二次回路に誘導により移行する。
- 雷サージ:
- 電気所内で、上記 1. で挙げたサージに対して、サージ発生源における対策と配電盤における対策を述べる。
- サージ発生源における対策:
- 金属シース付きケーブルを採用し、シースの両端を接地する。雷サージ、断路器開閉サージを低減する最も効果的な対策である。
- 低圧制御ケーブルは施工時に高電圧主回路の導線から距離を置く。
- 直流回路では、リレー回路のコイルに並列コンデンサやダイオードなどを接続し、開閉サージ電圧の発生を抑制する。
- 配電盤における対策:
- 避雷器又はコンデンサなどのサージ吸収装置を盤側端子に接続し、盤内へのサージ侵入を阻止する。
- 絶縁変圧器、中和コイルなどによって、盤側へのサージ侵入を阻止する。
- サージ発生源における対策:
絶縁設計での塩害対策
変電所の塩害対策は保守が容易ながいし類の過絶縁設計が基本であるが、海岸に近く、台風や季節風によりがいし類に付着する塩分が多い地域にある変電所では、電圧が高いほど、過絶縁設計だけではなく、活線洗浄などを組み合わせて対策することが多い。
その理由は、これらの地域では、活線洗浄などを組み合わせて対策するのに比べ、過絶縁設計のみで対策すると、がいし類を最大化する必要があり、電圧が高いほど、技術的に実現が困難、又は非常に高価となり、不経済となるからである。
地下変電所の設計
1. 地下変電所の設計に当たり、機器配置について、考慮すべき事項
地下変電所は電力需要密度や建設コストが高い都市部に建設されるため、一般の変電所に比べ、高信頼度かつ変電所スペースの縮小化を考慮した機器配置が必要である。
➀信頼度
事故が発生した場合は局限化することを基本に、電気的、機械的に隔離区分した機器配置(ユニット化)にすることが多い。
➁変電所スペースの縮小化:
変電所スペースの縮小化は、一般ビル地下での設置など立地面から必要である。
具体的には
・ガス絶縁機器(GIS)やガス変圧器などの縮小形機器を採用する。
・機器高さの近い機器を同一階に配置する。
・主要変圧器などの重量機器は、最下層に配置する。
・地上構造物により地下階の構造に制約がある場合があり、運転保守性、最終形態を考え、デッドスペースの少ない機器配置とする。
2. 地下変電所の設計に当たり、変圧器と電力ケーブルの防火対策について、考慮すべき事項
➀変圧器:
系統の短絡・地絡電流に耐える防火性能を有する変圧器仕様とする。
短絡・地絡電流が大きい超高圧などの系統に、油入変圧器を適用する場合は、高信頼度の保護・制御装置とすると共に、変圧器内部事故時のタンク内圧上昇でタンク破壊に至らないような対策が必要である。
・圧力上昇を低減するため、避圧空間をコンサベータ部に確保
・上部・下部タンク接続フランジ部を補強し、タンク強度を向上。
また、変圧器室は、耐火構造の壁や床で区画し、自動消火設備を備え、絶縁油が噴出した場合の処理のための集油槽を設ける。
従来の絶縁油に代わり、SF₆ガスにて絶縁し、不燃化を図るガス絶縁変圧器の適用も有効である。
➁電力ケーブル:
電力ケーブルは回線ごとに区画された洞道やピットに布設し、防火区画の貫通部は全て不燃材で埋める。
パーセントインピーダンス
パーセントインピーダンス(単位法)について詳しい解説はこちら。
電力系統では定格の異なる多くの機器や線路が接続されている。単位法では、これらの機器などの定数が統一的に記述されるので、取り扱いが容易となる。三相回路の場合には、線間電圧\(V_B\)[V]と三相容量\(P_B\)[V・A]を基準にとると、基準線電流\(I_B\)[A]と基準インピーダンス\(Z_B\)[Ω]は次式となり、インピーダンス\(Z\)[Ω]の単位法での値\(Z_{pu}\)[p.u.]は①式のように表される。
\(I_B=\displaystyle\frac{P_B}{\sqrt3V_B}\)[A] \(Z_B=\displaystyle\frac{V_B^2}{P_B}\)[Ω]
\(\displaystyle Z_{pu}=\frac{Z}{Z_B}\)[p.u.] ……①
変形すると、
\(\displaystyle Z_{pu}=\frac{P_BZ}{V_B^2}\)[p.u.]
百分率インピーダンス\(\%Z\)[%]は以下で与えられる。
ここで、基準インピーダンス\(Z_B\)[Ω]、基準容量\(P_B\)[MVA]、基準電圧\(V_B\)[kV]である。
\(\displaystyle \%Z=\frac{P_BZ}{V_B^2}\times100\)[%]
多くの電力機器の単位法でのインピーダンスは、機器の定格電圧と定格容量を基準として与えられる。この基準でのインピーダンスは、発電機や変圧器では定格容量や定格電圧によらずほぼ一定値となるので、定数の入力間違いなどの確認に便利である。たとえば、タービン発電機では、直軸過渡リアクタンスはほぼ0.2~0.4p.u.の間になる。
また、変圧器で接続された系統では、2次側のオーム値で表現されたインピーダンス\(Z_2\)[Ω]を、1次側に換算したインピーダンス\(Z_{2(1)}\)[Ω]にするには、変圧比(1次側\(n_1\)、2次側\(n_2\))に応じた換算が②式のように必要である。
\(Z_{2(1)}=\displaystyle\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2Z_{2}\)[Ω] ……②
一方、単位法では、一般に基準電圧として定格電圧が選ばれるので、基準容量が同じであればインピーダンス換算は必要ではない。ただし、異なった容量を基準とした単位法では、容量に応じた換算が必要であり、容量\(P_B\)[V・A]を基準とした単位法でのインピーダンス\(Z_{Bpu}\)[p.u.]は、容量\(P_{R}\)[V・A]を基準とした単位法でのインピーダンス\(Z_{Rpu}\)[p.u.]を用いて③式により求められる
\(Z_{Bpu}=\displaystyle Z_{Rpu}\times\frac{P_B}{P_R}\)[p.u.] ……③
基準線電流\(I_B\)[A]で単位法でのインピーダンス\(Z_{Bpu}\)[p.u.]に流れる三相短絡電流\(I_S\)は、
\(\displaystyle I_S=\frac{I_B}{Z_{Bpu}}\)[A]
- 電験3種過去問【2023年(前期)電力 問16】(変圧器二次側の百分率インピーダンスと定格遮断電流)
- 電験3種過去問【2022年(後期)電力 問6】(変圧器の百分率リアクタンス算出)
- 電験3種過去問【2022年(前期)電力 問16】(定格遮断電流と変圧器負荷分担の計算)
変圧器の並行運転
変電所の負荷の増大などに対応するため、複数台の変圧器を並行運転することが必要となる。変圧器の並行運転に必要な条件は、各変圧器が容量に比例した電流を分担し(条件①)、変圧器間の循環電流が実用上問題ないレベルとなる(条件②)ことである。
条件①を満足するためには、各変圧器の自己容量ベースの短絡インピーダンスが等しくなければならない。各変圧器を流れる電流の分担率は短絡インピーダンスに反比例する。
条件②を満足するためには、変圧比の差が小さいことが必要である。変圧比はタップにより変化するため、定格タップ以外の値についても確認する必要がある。また、結線(星形結線、三角結線など)により二次側電圧に位相の差が生じるため、これによる循環電流が生じないような結線・接続とする必要がある。
変電所母線の結線方式
単母線方式
所要機器及びスペースが少なくすみ、経済的に有利となる一方で、母線事故があった場合に当該母線が停止となり、また、母線側断路器等の点検のために、全停電となる場合があるなど、供給信頼性は低い。
複母線方式
母線切換のための断路器、鉄構等の設備が増え、所要面積が増加する一方で、機器点検や系統運用が容易となり、母線事故が発生しても、接続されている送電線や変圧器を他の母線に直ちに変更することができるなど、供給信頼性が高い。
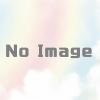
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません