電験1種(未)合格体験記(絶賛受験中です)
電験1種取得までの、学習方法、学習時間、葛藤、参考図書などを綴っています。
これからの取得を目指す方や、現在学習中の方の励みになれば幸いです。
ここに書いた学習時間はあくまで管理人自身の過程であって、各々の電気知識有無に大きく左右されると思いますので参考程度に気楽に読んでみてください。
目次
電験1種取得を決意した理由やその時点の知識
電験1種取得を決意した…のは運よく電験2種一発合格を果たしたからです。。。電験2種の2次試験学習中に自分の知識の低さに打ちのめされました。
本当に、ホントに運よく合格できたのは自分が一番よくわかっています。その時の記事は以下です。
ですので、電験2種の学習成果を固める(自分のものにする)ためにも、続けて1種を取得する必要があると考え受験を決意しました。
2種合格体験記にも述べましたが、2種取得を目指した理由は、転職のため、履歴書に箔をつけるためでした。1種の資格は実務には全く必要ありません。名誉資格と思って取得目指します。
1種取得のためのプラン
2種での反省を生かして、複数年度での合格をねらいます。
1次試験までの学習方法
2023年 1月頃~
電験2種の合格通知が届き、1種を受験するのかどうか悩み始める。
とりあえず、ブログ更新を継続。3種の過去問を解きながら1種の過去問もつまみ食い(ホントに少し)。ブログ更新をモチベーションに学習を続けてた(とおもう)。
2023年6月某日
今年受けないと、もう受けないのではないか。少しの危機感と、多少の勢いで、いつやるの?今でしょ!申し込み!ぽちっ
ここから、ブログ更新をストップして、過去問を解くことに集中。
理論が厳しいことが分かっていたので、理論の過去問を2009年~2013年の5年分実施。1日1問やったかやらないかのペース。解いた感じでは、手ごたえなく、初見で解ける問題はほぼなし。3周くらいしないと実力にならない感触だった。この時点で7月になっているので、理論を今年とるのはあきらめた方がよいと感じ始めた。
続いて、機械、電力、法規を3-5年分の過去問を古い方から実施。こちらは、ほとんど計算問題がないため1日数問程度のペースでやった。勉強が手につかないときは、サクッと解ける法規をやっていたので、法規を物量的にはたくさんやった感じ。手ごたえはなし。
1種過去問をやっていて感じたのは、定型の公式などについて問われることはほぼなく(知っていて当然ということだろう…)むしろ公式の導出が求められる。また重点用語が直接問われることも少なく、マニアックな重箱の隅をつつくような用語や知識を問われる(ほぼ対策不可能)。
ラスト1週間程度は2種の参考書をながら読みし、重点箇所とその解説にとにかく目を通しておく。
いざ本番へ。
電験1種1次試験(令和5年度/2023年度)自己採点結果
試験解答発表後に自己採点実施!
理論48点
電力59点
機械57点
法規59点
合格点は80点満点中の60%以上なので、48点以上で合格なので、合格?!
自分にとって最難関の理論は絶対に落ちたと思っていたのに、、うれしいけど、、うれしくないような複雑な心境です。複数年取得の計画が今年も狂った。
去年の電験2種に続き、1次試験の想定外一発通過!?
今すぐに2次勉強始めます。。。結構、いまゲッソリしています。気持ち、わかりますか?
1次試験受験体験記(試験中の心の叫び)は下の記事にまとめています。理論ボロボロです。
1次試験学習方法まとめ
1種の1次試験対策は、1種の過去問題をひたすら取り組むことで問題ありません。むしろ、1次試験は通過点なので、2次試験対策を行いながら、ついでに1次対策を行うことになります。
2種2次試験で計算する内容が、1種1次では問われるので、やはり2次レベルの対策は必須です。
電験1種の本丸は2次試験であるので、1次対策でしっかりと基礎を固めておかなければなりません。(不慮の1次合格はみなさん是非、避けてください。)
ラッキーで1次に合格(理論)してしまったため、あまり皆さんの参考にならず申し訳ないです。ただ、言えるのは、最後まであきらめず、山をはるにしても何かしら理論立ててやれば、女神がほほ笑んでくれる時もあるようです。ありました!
2次試験の学習方法(1回目)
8月末週(1次試験直後)からの暫定学習方針
1次合格判明の翌日から、学習開始。2種合格体験記での2次試験対策学習経験と、実践(本番試験)経験を踏まえて、とにかく過去問を無限周回するという方針で学習開始。
2次過去問をひたすら解く!が、選択と集中が大切!(2種受験経験より)
まず、過去問の出題傾向を調べると、電力管理は送配電で出題確率が6-7割を占めるので、ここを優先的に学習する。機械制御は自動制御の出題が100%なのでここを重点優先して学習する。
また、機械制御の学習にあたり、電力管理との共通項として、同期機、変圧器、誘導機(誘導機はほぼ機械だけか)などがあり、電力管理ではこの周辺の論説問題も多く出題されるので、総合力を上げるために重点学習項目とする。
水力、火力は出題確率が低いので、問題に触る程度に留める。パワエレはいったん捨てる。(パワエレに関しては、2種2次受験経験時には時間を無駄にした)
更に、年度単位ではなく、分野単位で一気通貫学習し、定着率を高める!2種合格体験記での学習では、参考書は初めから終わりまで、過去問も年度単位で実施していたが、これが辛かった。更には、参考書周回は短期決戦には向かない学習方法だったと、振り返って思う。なぜなら、参考書問題と本番試験問題の出題形式があまりに違うからだ。※ただし、参考書周回は全く無駄ではなかった、それは、確実に電験基礎学力を向上させてくれたし、1種受験の礎になっているからだ。
出題確率の高い分野を優先的に学習し、正答率を上げる!二次本番までこれをできる限り繰り返し、守備範囲と正答率をどこまで高められるかが勝負だ。
8月中の学習進捗
機械制御:自動制御を過去問13年1周完了。去年の2種2次学習時よりかなり進捗早い(去年の基礎知識ありのため)。2種では古典制御のみ取り組んでおり、近代制御は捨てていた。が、1種では近代制御のほうが出題率が高いため、1周で基本知識を何とか押さえる程度。身についてはいない。
電力管理:送電を過去問13年1周完了。対象座標法に苦しむ(多分2種にはあまり出ない)。教科書を引っ張り出してきて解答の意味を理解しながらすすめる。論説は分野横断で過去問に触れる。出題頻度の高い傾向をつかみ、出題率が高いところは、教科書を読み込み身に着けるよう心掛ける。
学習時間:平日は朝起きて30分-早起きできれば1時間、帰宅後30分-1時間、夕食後30分-1時間(できないことのほうが多い、眠い、テレビ見たい)。休日は朝1時間、昼2-3時間程度。家族サービスも必要だし、週末晩酌も必要なので案外学習時間は伸びない。
所感:2種2次学習より楽に感じる。2種2次で学習した知識が生きているからだと思う。かなりハイペースだと自分でも思うが、息切れしないように、最後まで走り切ろう!
9月
中旬、試験まで残り60日で過去問13年分を一通り周回完了(パワエレ除く)!かなり読み流す感じで計算方法は理解するが、複雑な計算はやっていない感じです。手ごたえは2割程度は解答できるが、それ以外は…
今後の方針
機械制御:同期機は円筒形回転子ならよいが、突極形は手に負えない感じなので、突極形は捨てる方針で。変圧器は得点源にしたい。誘導機は比較的得意だが巻線形電動機の凝った問題だと撤退したほうがよい雰囲気。
電力管理:論説は隙間時間で教科書を読み込む、頻出問題は何度か書き出し練習をしよう。頻出の送電、配電は正答率を上げるように過去問周回する。水力・火力は簡単な問題を得点源とできるように取りこぼしをしないように頑張る。
今後、2周目でどの程度正答率上げれるか、また論説は隙間時間で教科書を読み込むを引き続き継続しよう。
10月
合格通知と二次受験票が手元に届く。実感がわいてくる。残り30日、過去問2周目完了し正答率は50%程度か??問題により当たりはずれが大きすぎる。
電力管理に関しては、ここからは、参考教科書を読込み、例題を解く。計算問題強化しつつ、論説での正答率を上げていく。
機械制御は、的絞りの過去問をもう一周やって、過去問正答を100%に近づけることにした。現代/古典制御に関しては一日1問は解くようにして、理解を深め取りこぼししないようにする。
11月【本番月ラスト2週間】
電力主要項目(変電、送電、配電)と機械主要項目(同期機、誘導機、変圧器、制御)をもう一周!できる時間はないので、解説を読む!論説対策で教科書を読み込む。全く自信なしだが、走り切るしかない。
二次試験本番(1回目)
2次試験受験体験記(試験中の心の叫び)は下の記事にまとめています。
二次試験自己採点結果
電力管理 ~45点(甘採点)
機械制御 最大45点
電力・管理:120点、機械・制御:60点 合計180点。
二次試験の合格点は、108点以上/180点満点(100 点満点換算で60点以上)。
足きりラインは各科目平均点であり、平均点は合格点より低いはずなので
電力管理の合格点は72点、平均点は50%の60点と仮定
機械制御の合格点は36点、平均点は50%の30点と仮定
機械制御→45点、合格点以上
電力管理→記述問題ばっかりなので点数不確実だが45点?平均以下?平均点は3割~4割とのネット情報もあるのでまあワカラナイが、いずれにしても↓
合計→~90点?(不合格!)自己採点で+18点(論説で各6点増しあれば)上振れしないと不合格!
人事を尽くして…天命を待つのみです。天命の後、今後のこと考えよう…いまは自由時間を楽しもう…
悶々としたスキマ期間
受かってれば昇天!落ちれば再チャレンジと再学習の日々。
いずれにしても、ここまで学習した知識を自分の血肉にするためには、走り続けなければならない。
過去問を一日1問目標に。すこし休憩です。。2か月半疲れた…
とりあえず、休養時間とおもって、好きなことやります。
2次試験結果
2024年1月26日、HPで受験番号合否発表予定です…「結果は??」
合格情報は以下の通りです。
試験結果・合否内容等に関するお問い合わせにはお答えできませんので予めご了承ください。
試験名 令和5年度第一種電気主任技術者試験 二次試験 受験番号 ●●●●●●●●●●● 合否 合格者一覧にありません
一発で受からせてもらえるほど甘い試験ではなかった。ここから約10か月…再試験に向けて出直します。
2次試験学習方法(2周目)
2024年1月末日、2次試験結果不合格を知り、2周目の学習を開始。。
今回は1種、2種を通して初めて二次試験の対策期間が10ヶ月もある!?こんなロングマラソンに耐えれるのか?
とりあえず、過去問流しながら、歯が立たなかった計算問題をものにできるようにしていこう。。
2月
とりあえず、ブログ更新をモチベーションに一種電力管理二次試験過去問の論説を中心に再学習(ブログ記事化)。基本的には読むだけなので、簡単にこなせる。身についているかは不明。。。
3月
論説過去問をサクッと終えたところで、前二次試験で歯が立たず悔しかった対称座標法に取り組む。対象座標法の一種・二種過去問に取り組みながら、一応…理解…した…つもり。多分、実践レベルに全く達していない。簡単な条件付けるパターン、回路の定数を埋める等は取り逃さないレベルに仕上げていきたい。
計算に疲れたので、一種一次試験で二次論説に関連しそうな内容の過去問をつまみ食いしながら取り組む。(もちろんブログ記事化)
4月
どちらかというと、ブログ記事整理に重きをおきながら、一種一次の過去問に引き続き取り組む。中旬、このままではイカンということで、二次試験の計算問題過去問(電力管理)に取り組み始める。…ぜんぜん解けない。やばい…
簡単な問題を中心に取り組む。
5月
GWにかまけて、連休は机に向かえず。気分を変えて、機械制御分野の2次に取り組み始める。誘導電動機→変圧器と取り組み、難しい問題を除いて一周。同期発電機は難しそうだ…とばして、自動制御に取り組む。…完全に忘れているな…。
6月
自動制御を1周終えるころ、試験申し込み期限が近づく…受けないとこうか?不穏な考えもよぎるが、もったいないので当然申し込み。申し込みしたところで、少し気合がはいる。一日一問確実にこなしていこう…。
2次試験学習方法まとめ
1種の過去問題を、実際の試験時間で解くことは必須です。実際の試験では、とにかく時間がありません。
自分の場合は、機械制御のパワエレは捨て、参考書や過去問の計算問題をできる限り何周も解きました。問題を見た瞬間に、解答方法が浮かぶ瞬発力が身につくまで何度も周回が必要です。
記述問題は、分野が幅広いため、特別に対策は行わず、学習過程で身についた知識を記述できるように過去問ベースで練習しています。記述問題は当たりはずれが運しだいだと思います。
電験1種の2次試験対策は、計算に始まり、計算に終わる。
※応援メッセージいただけたら励みになります。何種でもよい受験者の方々。
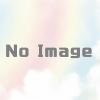
ディスカッション
コメント一覧
令和五年度の電験二種合格し、引き続き一種を目指しているアラ還と申します。今は一次理論を詰めてますが、なかなか難しくて捗りません。
ダラダラやってるといつまでも受かりそうにないのでそろそろ気合い入れなきゃと思ってます。ブログ拝見してやる気が出てきました。合格に向けて頑張りましょう!
アラ還さん
コメントありがとうございます。
本ブログが誰かのモチベーションになるのであれば
こちらも気合が入ります!
私は只今、令和五年度で涙をのんだ、
対称座標法を学習中です。
ブログにも順次反映しています、
一緒に頑張りましょう!