電験3種の過去問一覧
電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。 管理人の電験受験学習進捗に合わせて、順次更新していきます。過去問活用法については電験合格は過去問が近道をご覧ください。
他の過去問は↓
かなりの昔、学生時代に3種は取得していますが、ふと2種取得を思い立ち、忘却の彼方の知識を呼び覚ますべく3種過去問に取り組んだ記録です。
2022年度試験で2種取得できたため、現在は1種取得を目指しています!
電験2種を取得するまでの記録↓興味あれば見てみてください。
電験3種の過去問【年度別】
随時、追記中。〇は全問学習完了、△は半分完了、×は一部学習済みのものです。
| 試験年度 | 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |
| R5/’23(前) | × | 〇 | 〇 | × |
| R4/’22(後) | × | 〇 | 〇 | × |
| R4/’22(前) | × | 〇 | 〇 | × |
| R3/’21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| R2/’20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| R1/’19 | △ | △ | △ | 〇 |
| H30/’18 | △ | △ | × | △ |
| H29/’17 | △ | △ | × | △ |
| H28/’16 | △ | △ | × | △ |
| H27/’15 | △ | △ | × | △ |
| H26/’14 | △ | △ | × | △ |
| H25/’13 | △ | △ | × | △ |
| H24/’12 | △ | △ | × | △ |
| H23/’11 | △ | △ | × | × |
| H22/’10 | △ | △ | × | × |
| H21/’09 | △ | △ | × | × |
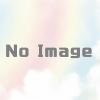
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません