電験2種過去問【2021年機械 問1】
【同期機】同期発電機の励磁方式《空所問題》
次の文章は、原動機で駆動され、電力系統に連系した、一般的な直流励磁の定速同期発電機の励磁方式及び励磁装置に関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
小型の同期発電機では界磁に永久磁石を使用することもあるが、中型から大型の同期発電機(以下、主発電機と呼ぶ)では界磁巻線に直流電流を通電して励磁する方法が適用される。
この直流電流(界磁電流)を供給する装置を励磁装置と呼び、近年では交流励磁機方式、又は静止形励磁方式が一般的である。また、この界磁電流の大きさを調整して主発電機の\(\fbox{(1)}\)や端子電圧を調整することを励磁制御という。
交流励磁機方式は、励磁電源として同期発電機を使用しており、この発電機を交流励磁機と呼ぶ。交流励磁機方式では、主発電機の界磁電流の増減は、交流励磁機の界磁電流の調整によって行われる。交流励磁機にも励磁が必要であるが、その電源としてさらに小型の発電機をもう一台使用する場合は、この小型の発電機を\(\fbox{(2)}\)と呼ぶ。
交流励磁機方式の一つにブラシレス励磁方式がある。ブラシレス励磁方式の交流励磁機の構造は\(\fbox{(3)}\)形であり、その出力は交流励磁機の回転子と同軸上に設置された半導体電力変換器整流されて、主発電機の界磁巻線に供給される。このため、この方式では主発電機及び交流励磁機に界磁電流を給電するための\(\fbox{(4)}\)とブラシが不要である。
静止形励磁方式では、サイリスタ素子を使用した電力変換器を使用する方式が近年一般的であり、サイリスタ励磁方式とも呼ばれる。サイリスタ励磁方式では、その電源を励磁変圧器経由で主発電機の出力回路(主回路)から得る\(\fbox{(5)}\)が多く採用されている。
[問1の解答群]
(イ)\( \displaystyle \text{有効電力}\) (ロ)\( \displaystyle \text{スリップリング}\) (ハ)\( \displaystyle \text{界磁遮断器}\)
(ニ)\( \displaystyle \text{他励方式}\) (ホ)\( \displaystyle \text{副励磁機}\) (ヘ)\( \displaystyle \text{回転界磁}\)
(ト)\( \displaystyle \text{整流子}\) (チ)\( \displaystyle \text{自励方式}\) (リ)\( \displaystyle \text{永久磁石}\)
(ヌ)\( \displaystyle \text{周波数}\) (ル)\( \displaystyle \text{無効電力}\) (ヲ)\( \displaystyle \text{変圧器励磁方式}\)
(ワ)\( \displaystyle \text{主励磁機}\) (カ)\( \displaystyle \text{回転電機子}\) (ヨ)\( \displaystyle \text{二次励磁発電機}\)
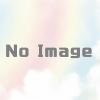

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません