電験2種過去問【2019年電力 問3】
【送電】送電容量に関する記述《空所問題》
次の文章は、送電容量に関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
送電線路により送電できる有効電力の最大値(本問題では「送電容量」という)は様々な制約を考慮して定められているが、それぞれの制約によって、送電容量を増加させるための対策は異なる。
電線温度の制約で定まる送電容量を増加させる方法としては、断面積が大きい電線や耐熱性の高い電線を用いることで、電線の\(\fbox{(1)}\)を大きくする方法がある。
送電線路に多導体を採用すると、断面積の合計値が同一である単導体の送電線路に比べ、送電線路の\(\fbox{(2)}\)が減少することから、過渡安定性、定態安定性(小じょう乱同期安定性)、\(\fbox{(3)}\)の制約から定まる送電容量も増加する。送電線路の\(\fbox{(2)}\)を減少させる方法としては、多導体の採用のほかに、並列して使用する回線数を増やす方法や、\(\fbox{(4)}\)の採用も考えられる。
電圧階級を上げると、電線温度の制約によって定まる送電容量は電圧に比例して増加する。また、ある位相差角のときに送電できる有効電力が電圧の\(\fbox{(5)}\)にほぼ比例することから、電線階級を上げることにより、過渡安定性、定態安定性(小じょう乱同期安定性)の制約から定まる送電容量も増加させることができる。
[問3の解答群]
\(\small{\begin{array}{ccc}
(イ)&線間距離 &(ロ)&コロナ電圧 &(ハ)&三乗 \\
(ニ)&電圧安定性 &(ホ)&一乗 &(ヘ)&弛度 \\
(ト)&周波数上昇 &(チ)&直列コンデンサ&(リ)&リアクタンス \\
(ヌ)&直列リアクトル&(ル)&対地静電容量 &(ヲ)&並列コンデンサ\\
(ワ)&二乗 &(カ)&周波数低下 &(ヨ)&許容電流 \\
\end{array}}\)
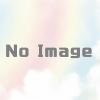

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません