電験2種過去問【2021年電力管理 問5】
【配電】地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法《記述問題》
地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法について、次の問に答えよ。
(1)表1は、CVケーブルの絶縁劣化である水トリーに関する絶縁劣化診断法についての記述である。表中の(A)~(D)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。
(2)表2は、地中送電線の事故点測定法である「マーレーループ法」と「パルスレーダー法(送信形パルス法)」の原理並びにそれぞれの長所並びに短所についての記述である。表中の(E)~(I)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。
表1
| 絶縁劣化診断法 | 原理 |
| 損失電流法 | 水トリー劣化ケーブルの充電電流の中に、課電電圧と同位相の損失電流成分が含まれることから、この損失分を測定し劣化の状況を把握する手法である。劣化したケーブルの測定波形は\(\fbox{(A)}\)歪みが観測される。 |
| \(\fbox{(B)}\)電荷法 | 最初に\(\fbox{(C)}\)課電によって水トリー部に電荷を蓄積させ、次に\(\fbox{(D)}\)課電で蓄積した電荷を放電させる、\(\fbox{(C)}\)課電と\(\fbox{(D)}\)課電を組み合わせた手法である。検出された電荷の量は、水トリーの数や長さによって変化するため水トリーの発生状況を検知することができる。 |
表2
| 事故点測定法 | 原理 | 長所 | 短所 |
| マーレーループ法 | \(\fbox{(E)}\)の原理により、事故点までの抵抗値を高精度に測定する方法である。 | ・導体抵抗を利用した\(\fbox{(E)}\)法のため、測定精度が高く、誤差は1%程度以下である。 ・ケーブル事故の多くが\(\fbox{(F)}\)地絡であるため、適用範囲、使用実績が最も多い。 |
・\(\fbox{(G)}\)事故に適用できない。 ・\(\fbox{(H)}\)同時地絡事故のように並行健全相がない場合、測定は困難である。 |
| パルスレーダー法(送信形パルス法) | 事故ケーブルにパルス電圧を加え、健全相と異なるサージインピーダンスをもつ事故点からの\(\fbox{(I)}\)パルスを検知して、パルスの伝搬時間を測定し、事故点までの距離を求める方法である。 | ・並行健全相が不要であるので、\(\fbox{(H)}\)同時地絡事故の測定に適している。 ・線路こう長がはっきりしていない場合でも測定できる。 |
・測定操作、パルス波形の判読に熟練を必要とする。 ・測定精度が若干低い。(誤差は一般的に2~5%) |
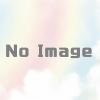

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません